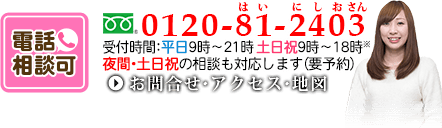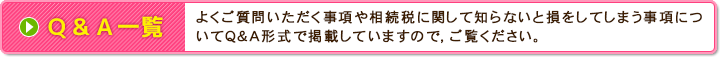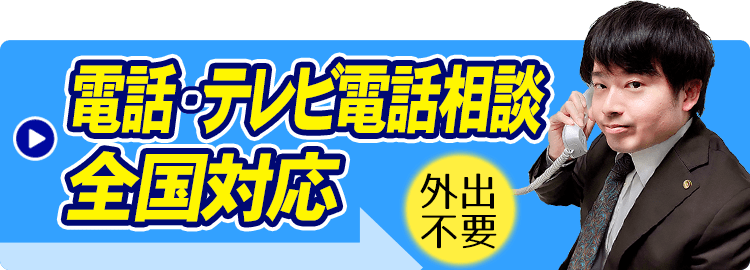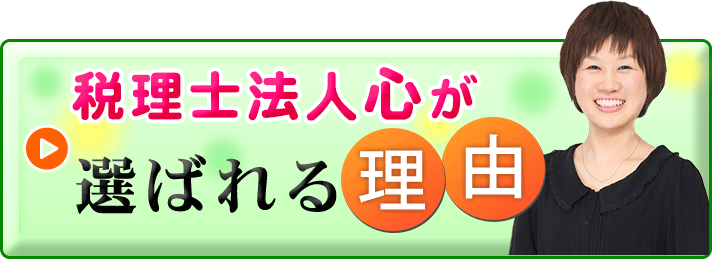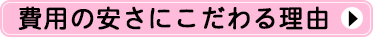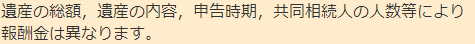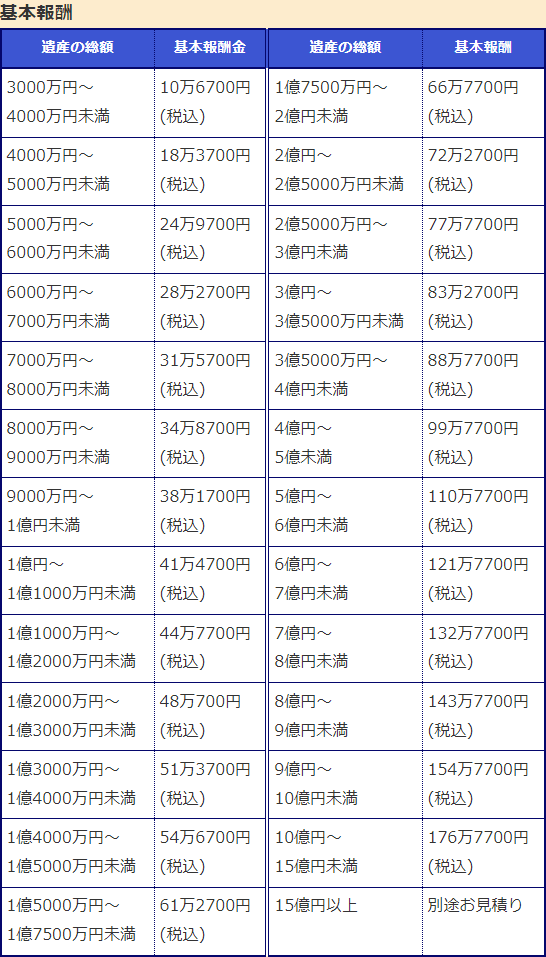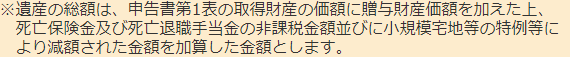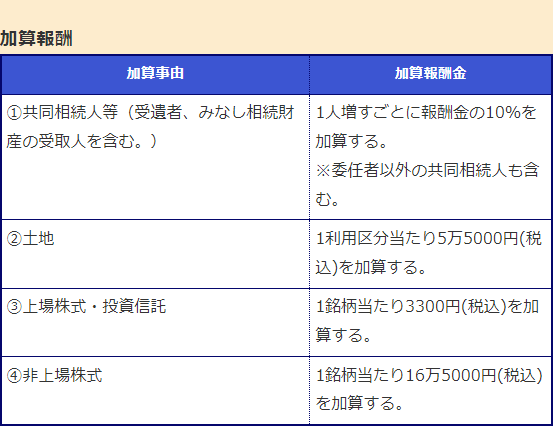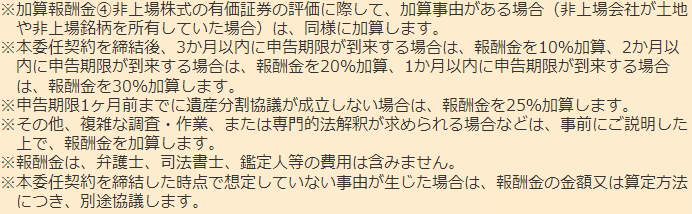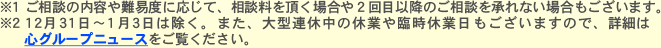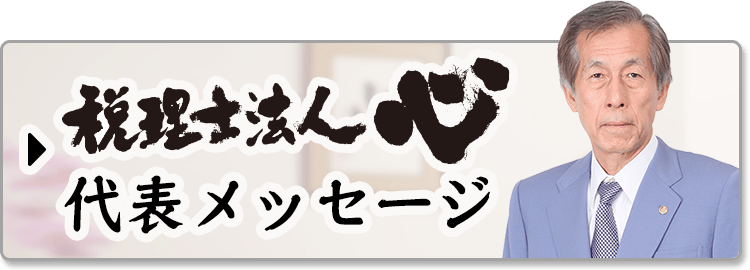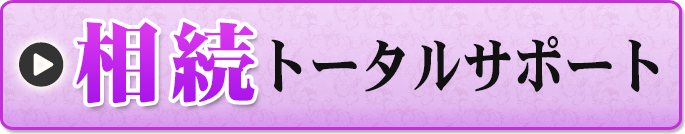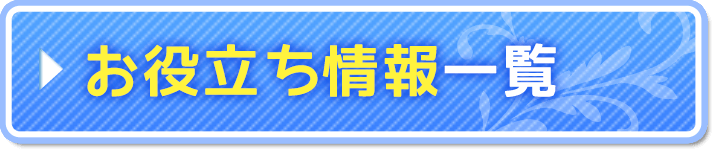「相続税の計算」に関するお役立ち情報
宝石や貴金属を相続した場合の相続税
1 宝石や貴金属は相続税の対象となる
相続税は、原則として、被相続人(亡くなった人)の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その財産の評価額の分を計算上考慮します。
ここでいう「財産」とは、現金、預金・貯金、有価証券、宝石、土地、家屋といったものから、貸付金、特許権、著作権などの金銭的評価が可能な経済的価値があるものすべてが該当します。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
つまり、宝石や貴金属もまた、売買の対象となるような経済的価値のあるものに該当しますので、相続税の対象となります。
このとき、「宝石が小さい」「ずいぶん前に買ってくたびれている」「有名ブランドではない」といった理由で、高額で売れないような事情があるとしても、原則として、相続税の対象となるので、申告に漏れがないように注意が必要です。
2 相続税評価の原則は相続開始時
相続税の評価をする際には、金銭的評価(「○○円」のように日本円単位に換算)をする必要があります。
その際に、基本的には、相続開始時(被相続人が亡くなった日)を基準として評価を行います。
つまり、宝石や貴金属についても、原則としては、購入時のきれいな状態ではなく、相続開始時の購入から時間が経過した状態のもので評価を行います。
逆にいえば、購入時に廉価だった場合や、無料でもらったものであるものが、相続開始時に価値が上がっている場合や、相続開始後に価値が下がり続け、相続税申告時に価値が下がっている場合でも、相続開始時を基準として評価する必要があります。
3 宝石や貴金属の評価方法には、いろいろある
⑴ 質屋等での査定
質屋や買取専門業者の査定を出してもらい、買取り(金銭に変える場合の)価格を確認し、その金額を出すことも有効です。
多くの場合は無料で査定を行っていただけます。
その場合は、できれば書面等で記録に残すことをしてもらえれば、申告時の参考資料とすることができます。
しかし、業者によっては実際の買取りがない場合は、書面にできないと断る場合もあります(電卓に表示するのみで済ませるところもあるようです)。
また、一店舗だけでなく、複数の店舗で見積りを立てておくことが、正確な数字を出すうえで重要です。
⑵ 宝石鑑定士への依頼
⑴のような業者が見つからなかった場合や、高価すぎて評価が難しい宝石や貴金属の場合、宝石鑑定士のような鑑定そのものを業務としている人へ鑑定をお願いすることも考慮に入れるべきでしょう。
宝石鑑定士に依頼を行えば、鑑定価額に参考にした、「売買実例価額」や「精通者意見価格」といった根拠資料を取得することができます。
ただし、鑑定の場合は⑴の査定と異なり有料で実施する場合が多いですので、実施前に料金等を確認しておくといいでしょう。
⑶ 実際の売却価格
相続人が売却の意向を固めているのであれば、実際に売却手続きを行い、その際に、売却できた金額を評価額とすることも可能です。
その場合は、買取りの証明になるような領収書などを相続税の申告時の参考資料として添付することができます。
ただし、安く売れば評価額が下がり、相続税の節約になるかといえば、そうではありません。
取引一般の価格よりあまりに乖離した廉価で売却した場合には、その価格では評価することは危険です。
つまり、実際に売却する場合でも、⑴や⑵のように客観的評価額を調べたうえで、売却手続きをとられる方がいいでしょう。
4 ご不安があれば税理士に相談を
上記のように、宝石や貴金属の相続税の評価はあいまいな部分が多く、困難である場合があります。
そして、評価を誤って申告してしまうと、税務調査が入ったり、追加課税がされる場合もあります。
そのため、もし、相続した財産の中に宝石や貴金属があった場合には、自分ひとりで判断したりせず、一度税理士にご相談されることをおすすめいたします。
相続税はどうやって計算するのか 配偶者に対する相続税額の軽減